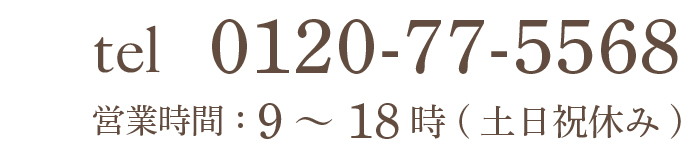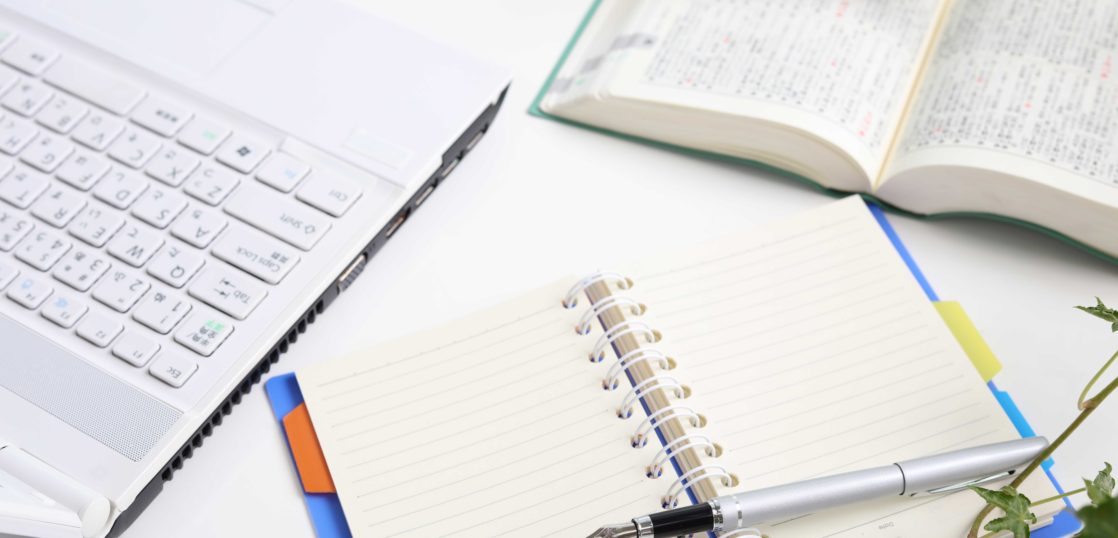宝石店や百貨店などで店員と顧客がダイヤモンドについて会話をするとき、ダイヤモンドに特有な用語が出て来ます。またカタログ販売やネット販売においてもダイヤモンドを説明するとき、しばしば使われる特有な用語があります。代表的な用語のひとつに4Cがあります。以下、ダイヤモンドに特有な用語をとりあげ、解説します。
4C
ダイヤモンドの価格算定を行うには、先ずダイヤモンド自身の品質評価をしなければなりません。その品質項目が4Cです。
- カラット(Carat)
- カット(Cut)
- カラー(Color)
- クラリティ(Clarity)
各項目を英語で表記したとき、4項目の頭文字がいずれもCで始まることから、4Cと呼ばれています。現在、鑑別鑑定機関において、カラットとカットは自動測定装置で計測されています。カラーとクラリティは訓練された専門家によって評価されています。
キュレット
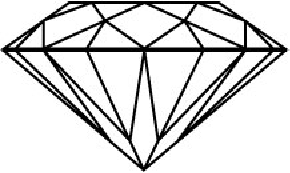 ほとんどのダイヤモンドは、ラウンド・ブリリアント・カットと呼ばれる独特な形状をしています。その形状は右図の通りです。下側は円錐形、上側は円錐台です。
ほとんどのダイヤモンドは、ラウンド・ブリリアント・カットと呼ばれる独特な形状をしています。その形状は右図の通りです。下側は円錐形、上側は円錐台です。
下側の円錐形では、ファセット(平らな研磨面)が1点に集まっています。その部分がキュレットです。
キュレットは、ファセットが1点に集まり、とがっています。ですから、破損を避けるために通常はごくわずかにその先端を削っています。その先端を余り深
く削り過ぎると、光がその個所から逃げて行きますので、好ましくありません。従って、肉眼で見えにくい程度の削りが良いとされています。
ブライトネス
光りの輝きを意味します。ダイヤモンドを美しくきれいに見せる最大の要因です。ダイヤモンドを上から見ると、白くまぶしく光り輝いています。
このブライトネスを最大限に引き出すには、ダイヤモンドをラウンド・ブリリアント・カットの形状にする必要があります。上からダイヤモンドに入った光が下側のファセットに当たり、反射して元に帰ります。光が元に戻ることから、白くまぶしく光り輝くブライトネスが生まれます。
シンチレーション
一般には星のまたたきという意味です。ダイヤモンドにおいては、ダイヤモンドを動かすとき、人の目が動くとき、光源が動くとき、ダイヤモンドのファセットの平面からキラ、キラと光が反射します。この現象を言います。
シンチレーション効果を上げるには、ファセットの面数を増やせば良いと思われますが、必ずしもそうではありません。ファセットの面積を余り小さくすると、シンチレーション効果が薄れてしまいます。これは実験で確かめられています。
逆にファセットの面積を余り大きくすると、シンチレーション効果は低減してしまいます。シンチレーション効果をうまく引き出すには、適度な面積のファセットとその数が必要ということになります。
ファイア
宝石の内部から発する虹色現象をいいます。ダイヤモンドを見て、美しいを感じさせる三要因のひとつです。ブライトネスとシンチレーション、そしてこのファイアがダイヤモンドを美しく見せている要因です。
ファイアは宝石業界の用語で、中学校や高等学校の理科、物理の世界では「分散」と呼ばれています。身近な例では、ガラスプリズムを通った光が白い壁に虹色に分布して見える現象です。
ダイヤモンドへ天井からの光を採り入れて、注意深く観察すると、赤色、橙色、黄色、緑色、青色、藍色、紫色が見られます。藍色の観察はなかなか難しいです。
Ⅰ型およびⅡ型
すべて同じように見えるダイヤモンドも紫外線の透過の程度を測定すると、2種類に分けられます。Ⅰ型ダイヤモンドとⅡ型ダイヤモンドです。ほとんどの天然ダイヤモンドはⅠ型です。合成ダイヤモンドはⅡ型です。Ⅰ型ダイヤモンドは紫外線を通しにくい性質を持っています。Ⅱ型ダイヤモンドは紫外線を通し易い性質を持っています。
現在、合成ダイヤモンドが宝飾品の中に少しずつ浸透して来ています。この合成ダイヤモンドを天然ダイヤモンドと識別する第1段階として、紫外線の透過性の程度を利用しています。すでにダイヤモンド・スクリーンなどの名称で機器が販売されています。
GIA
GIAは「Gemological Institute of America」の略称です。日本語表記では、米国宝石学協会または米国宝石協会です。
1931年にシプリー(Shipley)が設立しました。シプリー自身は宝石の小売商でした。その当時のダイヤモンドの取引、売買では品質の表示が明確でなく、統一された基準はありませんでした。また、シプリーは宝石商、宝石業界全体の知識が低いことを認識し、改革が必要と考えていました。このような背景から、シプレーはダイヤモンドの品質基準の確立と宝石学の教育を目指してGIAを設立しました。
そして、1940年代にシプレーはダイヤモンドの評価について、4Cで行うことを提唱しました。現在のような明確な4Cではありませんが、ダイヤモンドを評価する4Cという基本概念を打ち出しました。
その後、1953年、リディコート(Liddicoat、第2代会長)はダイヤモンドのカラー表示をD~Zに分類することを決定、数年後、クラリティをVVSやVSなどに分類することを決定しました。さらに2006年、カットについてグレーディング(等級)・システムを導入しました。
そして現在に至り、GIAによるダイヤモンドの評価システムが世界標準となりました。GIAは長い時間と多くの人とたくさんのお金を投入して、ダイヤモンド評価の世界標準を作り上げたのです。
モース硬度10
多くの人は、「ダイヤモンドはものすごく硬い」というイメージ、思いを持っています。
すべての物の中でダイヤモンドは最も硬い、と大多数の人は思っています。確かにその通りです。ダイヤモンドに限らず、宝石はすべて硬いです。指で押して窪むような宝石はありません。ルビーもエメラルドも水晶も硬いです。
ここで、ダイヤモンドは他の宝石と比べて、どの程度硬いのだろうかという疑問がわきます。硬さの相対的な尺度を考案したのがドイツの鉱物学者・モースです。モースは硬さの目安となる10種類の石(鉱物、宝石)を挙げました。一番軟らかい石をモース硬度1とし、滑石をあてました。そして最も硬い石をモース硬度10とし、ダイヤモンドをあてました。
世界の宝石業界では、宝石の硬さを表す場合、モース硬度で表示します。ダイヤモンドのモース硬度は10です。ルビーのモース硬度は9です。宝石としてはモース硬度7以上が望ましいと考えられています。ダイヤモンドもルビーも充分な硬度を持っているといえます。
ダイヤモンドとルビーの硬さを比較した場合、モース硬度では10と9で、その差は1です。この差の数値1が大きな意味を持っています。古物として帰って来るダイヤモンドのリングとルビーのリングを観察すると、大きな差を発見します。貴金属のスリ傷状態から数十年間使われてきたと推測される両リングを比較すると、ファセット・ライン(ファセットとファセットが接するライン、線)に大きな差があります。
ダイヤモンドのファセット・ラインはシャープで元のままです。ルビーのファセット・ラインは少しギザギザになってすり減っています。やはりダイヤモンドは硬いです。宝石の王様と言われるようにダイヤモンドは圧倒的に硬いです。