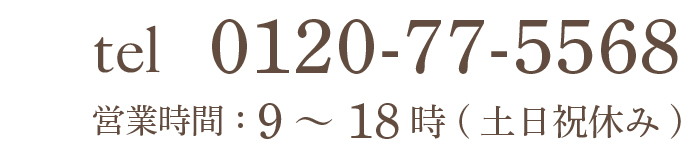実は全く別の石:ヒスイ(硬玉)とネフライト(軟玉)
ヒスイ(翡翠、ひすい)の色のイメージとして、ほとんどの人は緑色を想像すると思います。緑色のヒスイは日本や中国で人気があります。
古くからヒスイは「玉(ぎょく)」と呼ばれていました。玉には2種類があり、ひとつは硬玉(こうぎょく)、もうひとつは軟玉(なんぎょく)です。両者は混同されて来た歴史があります。
硬玉と軟玉は外観が似ています。しかし両者はまったく別な種類です。硬玉がヒスイで、軟玉はネフライトのことです。英語で「玉」はジェード(Jade)と呼ばれています。硬玉はジェダイト(Jadeite)、軟玉はネフライト(Nephrite)と表示されます。最近ではウェブサイトで、ヒスイをジェダイトと表示していることもあります。
それぞれの数値は7と6.5です。0.5の違いですが、硬玉はより硬いです。
中国では古くからヒスイの彫刻品が作られて来ました。しかし、ヒスイ(硬玉)の彫刻品と思われていたものの多くはネフライト(軟玉)であることが判りました。

ヒスイは中国で産出しません。ネフライトは産出します。本物のヒスイの彫刻品の場合、原石はミャンマーから輸入されて中国で加工されたものです。
ヒスイ(硬玉)もネフライト(軟玉)も彫刻に関して優れた素材となります。両者とも粘り強い性質を持っています。打撃や衝撃に対して強い性質を持っています。
特性表の第2番目に組織の項目があります。硬玉は粒状組織、軟玉は繊維状組織です。
水晶のように単結晶で形成されている場合、1個所に強い打撃を受けると、破壊が一気に全体に伝播して破損に至ります。
ところが粒状や繊維状の組織は多結晶であり、ひとつの粒、ひとつの繊維で破壊が留まる傾向にあります。破壊が全体にまで及びにくいです。それゆえ、彫刻に向いている素材になります。
特性表の第3番目に本体を構成する鉱物名が記載されています。両者の本体は異なります。それぞれヒスイ輝石と角閃石です。本体を構成する鉱物が異なりますので、特性表の屈折率や比重も違う数値を示しています。
緑だけではない多彩なヒスイ
ヒスイの色の話を深堀していきます。一般にヒスイは緑色のイメージがあります。しかし、ヒスイは多彩な色で産出します。逆に産出しない色はピンク色とブルー色に限られます。
写真の下側領域(約90度領域)は緑色系で占められています。
良質のヒスイは鮮やかな緑色です。半透明な鮮緑色が最高の評価を受けています。
鮮やかな緑色の発色原因は微量に含まれているクロム(Cr)元素です。ヒスイ(硬玉)によく似ている緑色のネフライト(軟玉)の発色原因は鉄(Fe)元素です。鉄による緑色は鮮やかさに欠けます。暗緑色に見えます。

写真の上側領域の中心部には赤色のヒスイが見られます。赤色の発色原因は酸化鉄と考えられています。この酸化鉄は本体であるヒスイ輝石の中に存在しているわけではありません。ヒスイは粒状組織をしています。粒と粒の間には境界があります。この境界に入り込んだ不純物が酸化鉄です。
写真の中央の左に白色のヒスイが見られます。ヒスイの本体、粒の境界に不純物が存在しない場合、白色となります。透明性が増すと、氷のような外観を示します。このようなヒスイは、アイス・ジェダイトと呼ばれています。
アイス・ジェダイトも粒の集合体ですから、粒界で光が散乱され、水晶のような透き通る透明性までには至りません。
写真の右上側には紫色のヒスイが見られます。紫色系のヒスイはラベンダー・ヒスイなどと呼ばれています。発色原因はヒスイ輝石の中に含まれている鉄(Fe)元素、あるいはマンガン(Mn)元素と推測されています。
ヒスイの中には黒色のブラック・ジェダイトもあります。一般に宝石の黒色は本体に含まれる不純物の量が多いことに原因しています。緑色や青色の宝石も不純物が多過ぎると、外観は黒色に見えます。
ヒスイの黒色の原因は他の宝石と異なります。ヒスイの黒色は粒界に入り込んだカーボン(C、炭素)によるものです。カーボンの量が少ないと、灰色になります。
ヒスイは粒状組織をしています。ですから、粒と粒の間には粒界が存在します。このような組織は染色され易いです。薄い緑色のルースを人工的に染色して、濃い緑のヒスイに仕上げる着色処理がしばしば行われています。このヒスイはCヒスイ(Cタイプ・ヒスイ)と呼ばれています。
外観を向上させるために無色透明な樹脂(エポキシ樹脂など)を浸透させることも行われています。このヒスイはBヒスイ(Bタイプ・ヒスイ)と呼ばれています。
CヒスイやBヒスイ以外、何も処理されてないヒスイはAヒスイ(Aタイプ・ヒスイ)と呼ばれています。
処理ヒスイと無処理ヒスイの違いは色溜まりなどで容易に判ることもありますが、確実に判定するには、鑑別機関が保有する装置(FTIR装置など)を利用する必要があります。