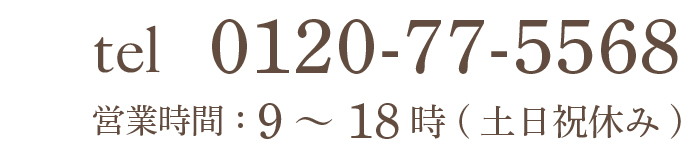Contents
シリカからできる石イロイロ
シリカとは二酸化ケイ素(SiO2)のことです。シリカで造られている宝石、準宝石は数多くあります。宝石の例はオパールです。準宝石の例はアメシスト(紫水晶)やシトリン(黄水晶)、メノウ、オニキスなどです。準宝石とは希少性や硬さの点において、宝石と比較すると、少し低いと言えます。
シリカで造られている宝石、準宝石をまとめてシリカ・グループ・ストーンと称しています。このグループは大きく次の3種類に分類されます。
(1)非晶質(非結晶)系
(2)結晶系
(3)潜晶質系
非晶質とは、例えばオパールを構成している元素(ケイ素と酸素)の並びが不規則である場合をいいます。結晶とは、例えばアメシストを構成している元素(ケイ素と酸素)の並びが規則的である場合をいいます。潜晶質とは、例えばメノウを構成している元素(ケイ素と酸素)の並びが規則的であるが、その結晶の大きさが非常に小さい場合をいいます。
シリカ・グループ非晶質系の代表オパール
シリカ・グループにおける非晶質系の代表はオパールです。オパールの色は様々です。赤色、橙色、黄色、緑色、青色、紫色など多様な色が見られます。
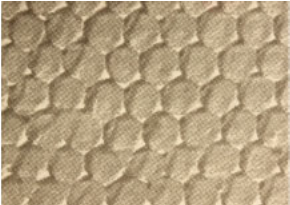
超微粒子の組成はシリカで構成されています。超微粒子と超微粒子の隙間もシリカですが、少しだけ組成が異なると推測されています。水分の量がわずかに多いと思われます。
オパールの虹色はシャボン玉と同じ原理
超微粒子が整然と連続して並んでいると、ひとつの薄い膜とみなすことができます。少しだけ組成が違う隙間も薄い膜とみなすことができます。
薄い膜が組成の異なるものと接していると、虹色が生じます。この虹色は私達の身近で見られます。それはシャボン玉です。シャボン玉は薄い水の膜と組成が異なる空気と接しています。その結果、干渉と呼ばれる現象が起こって、虹色が生じます。
シャボン玉の色は、薄い水の膜の厚さによって変化します。少し厚いと赤色、橙色になります。少し薄いと青色、紫色になります。
オパールの色も赤色、橙色から青色、紫色まであります。このように多様な色が生じる理由は、オパールを構成する超微粒子のサイズに原因していると考えられています。少しサイズが大きいと、赤色、橙色になります。少しサイズが小さいと、青色、紫色になります。
シリカ・グループ結晶系の代表水晶
シリカ・グループにおける結晶系の代表は水晶です。水晶は多くの人に知られている石です。通常、水晶と言えば、無色透明な石を指します。水晶は石英とも呼ばれますが、両者の区別は明瞭ではありません。単に透明できれいな石の場合は水晶と呼ばれることが多いです。半透明や不透明、きれいさが落ちる石の場合は石英と呼ばれます。
宝石市場で流通している水晶の色は、紫色のアメシスト(紫水晶)、黄色のシトリン(黄水晶)が主力です。
アメシストの紫色やシトリンの黄色の発色は、鉄分が影響していると考えられています。
しかし、鉄分の存在に加えて、自然の中で放射線や熱の影響を受けて、これらの色が発現していると推測されています。
シリカ・グループ潜晶質系の代表 瑪瑙(めのう)と玉髄(ぎょくずい)
シリカ・グループにおける潜晶質系の代表は、瑪瑙(めのう)と玉髄(ぎょくずい)です。最近では、瑪瑙の英語表記であるアゲート、玉髄の英語表記であるカルセドニーを使う人も多いです。ここではアゲートとカルセドニーと表記します。
アゲートとカルセドニーの違いは外観だけです。外観が不均質の場合はアゲートと言います。外観が均質の場合はカルセドニーと言います。
アゲートの典型的な例は縞模様です。白色と褐赤色の縞模様が見られる石はサードニクス(サードオニキス)と呼ばれています。白色と黒色の縞模様が見られる石はオニキスと呼ばれています。
最近、白色の縞模様がほとんど見られないか、あるいは白色の縞模様がまったく無い石に対してオニキスと表示して場合が結構あります。このような石は本来、ブラック・カルセドニーと表示されるのですが、時代と共に名前も変化する一例かもしれません。
カルセドニーに属する石としてアクセサリー市場でしばしば出会う名前はカーネリアンです。この石の外観は半透明で黄橙色から橙赤色です。全体は一様な色です。発色原因は鉄と推測されます。
カーネリアンの他にカルセドニーに属するいろいろな色の石があります。黄色のイエロー・カルセドニー、灰青色のブルー・カルセドニー、黒色のブラック・カルセドニー、褐赤色(茶赤色)の場合は特別にサードと呼ばれています。
カルセドニーの中で比較的価格が高い石は緑色のクリソプレーズです。一見すると、良質のヒスイのような外観です。この石の主要産地はオーストラリアです。このためにオーストラリア・ヒスイとして販売されていることもあります。クリソプレーズはヒスイではありません。オーストラリア・ヒスイという名称は好ましくありません。知らない人はクリソプレーズをヒスイと誤認する恐れがあります。
クリソプレーズの鮮やかな緑色の発色原因はニッケル化合物と考えられています。
アゲートもカルセドニーも微粒子の集合です。微粒子と微粒子の間に有機染料を染み込ませることが可能です。ですから、市場には染色された鮮やかな紫色や青色のアゲートが流通しています。
シリカは私達の大地を構成する重要な鉱物です。通勤や通学で大地を歩くと、必ずシリカを踏むことになります。シリカの中の美しい色を示すものが、オパールやアメシスト、シトリン、アゲート、カルセドニーとして店頭に展示されています。