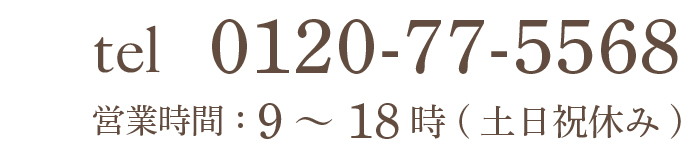Contents
大きく3種類のシリカ
シリカ・グループとは、シリカ(二酸化ケイ素、SiO2)という組成(成分)を持ついくつかの宝石、準宝石のグループ(集まり)を言います。
具体的な例としてオパール、アメシスト、シトリン、オニキス、ブルー・カルセドニーなどが挙げられます。
このシリカ・グループ・ストーンは大きく3種類に分けられます。次の通りです。
(1)非晶質系:原石の状態は塊状です。外観は透明から半透明です。
(2)結晶系 :原石の状態は六角柱状です。外観は透明です。
(3)潜晶質系:原石の状態は塊状です。外観はほとんど半透明です。
表面は美しい虹色のオパールでも側面が重要
非晶質系に属する宝石はオパールです。先ず、このオパールの鑑別から始めます。多くの人にとってオパールといえば、美しい虹色を示す宝石とのイメージがあります。オパールは日本人に人気がある石です。確かに青色や緑色、オレンジ色などの多彩な色がひとつの石の中で同時に見られるオパールは、きれいで魅力的です。
ひとつの石の中に部分的に青色、緑色、オレンジ色などの虹色が見られる現象は遊色効果(プレイ・オブ・カラー効果)と呼ばれています。オパールの最大の魅力はこの遊色効果が見られるところにあります。
遊色効果が見られたら、今、目の前にある石はオパールと判定しても間違いありません。
しかし、オパールを鑑別(観察している石の名前が何であるか、天然石か合成石かなどを判定すること)する場合、注意を要することがあります。
それはオパール・ダブレットとオパール・トリプレットと呼ばれる製品が市場に出ているからです。オパールは薄い層で産出することも多く、例えば厚さ1ミリほどの薄いオパールを活かすために他の素材(ガラス、水晶など)と貼り合わせることがあります。


オパールを鑑別するときは、「側面から観察すること」が鉄則です。オパール・ダブレットやオパール・トリプレットを側面から観察すると、接着した面が1本または2本の黒い線として見られます。比較的厚いオパールの原石からカット(切断、研磨)された製品では、側面から観察しても1本または2本の黒い線は見られません。
オパール・トリプレットにおいて、最下部に黒色の素材を貼り合わせる理由は、外観をブラック・オパールに似せるためです。一般に見られる白色系のホワイト・オパールよりもブラック・オパールは高価です。この理由のために最下部に黒色の素材を貼り合わせます。そしてそのオパール・トリプレット製品を上から見ると、黒色を背景にして遊色がより映えることになります。
きわめて美しい合成オパールを鑑別する
オパールの鑑別において、オパール・ダブレットとオパール・トリプレットを見破ることは重要です。さらに合成オパールが課題になります。天然オパールに対して、現在、フランスや日本で合成オパールが生産されています。これらの合成オパールは美しい虹色、遊色効果を示します。
フランスで造られた合成オパールは虹色の部分を10倍のルーペで拡大すると、鱗(うろこ)状の模様が見られます。この模様は写真では認識しにくいので、描画で示します。

日本でも合成オパールがたくさん造られています。このオパールの外観はきわめて美しく、日本でも外国でも人気があります。この日本製の合成オパールは、側面から観察すると、斑が縦状に伸びた形状をしています。この特徴が鑑別の目安になります。
アメシストやシトリンをガラスと鑑別する
シリカ・グループ・ストーンの結晶系に属する石は、アメシストやシトリンなどが挙げられます。アメシストは日本語表記では紫水晶、シトリンは黄水晶と呼ばれています。
これらの石を鑑別する場合、バイオレット(紫色)・ガラスやイエロー(黄色)・ガラスが課題となります。
アメシストやシトリンを白い壁を背景にして、10倍のルーペで内部を観察すると、薄い部分と濃い部分の色ムラが見られます。その濃淡の境界は直線状です。バイオレット・ガラスやイエロー・ガラスでは見られない特徴です。
比較的身近な石のシリカ・グループ 潜晶質の石
シリカ・グループ・ストーンの潜晶質に属する石は、オニキス、ブルー・カルセドニーなどが挙げられます。オニキスは白色と黒色の縞模様を持っています。このように縞模様を示す石はすべてメノウと呼ばれています。メノウは英語表記ではアゲートです。
ブルー・カルセドニーは半透明、曇り状です。鮮やかでない淡い青色をしています。外観は縞模様が見られず、均質な感じです。このような石はすべて玉ずいと呼ばれています。玉ずいの英語表記はカルセドニーです。
メノウ(瑪瑙)は普通に出会う石です。世界や日本の多くの地域で産出する身近な石です。ですから、価格は比較的安価です。メノウの鑑別は、カボッション・カット(山形形状)、縞模様、半透明がポイントです。
カルセドニーも普通に見られる石です。比較的安価です。カルセドニーの鑑別は、カボッション・カット、均質外観、半透明がポイントです。カルセドニーの場合、名称は外観の色の名前を頭に付けて表示されます。例えば、ブルー(青色)の場合は、ブルー・カルセドニー、イエロー(黄色)の場合は、イエロー・カルセドニーと表示されます。