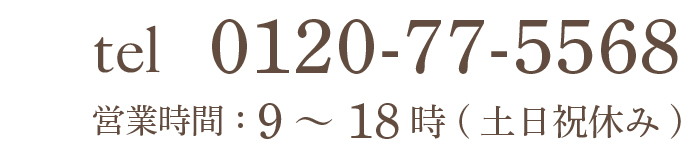パライバ・トルマリン
1989年、ブラジルのパライバ州で発見されたことからこの名前が付けられました。鮮やかな青色をしたトルマリンです。
この石の発色は銅に原因していることが判りました。さらにマンガンが鮮やかさに関与していると推測されています。銅の含有率(パライバ・トルマリンの中に含まれている銅の割合)は最大で5.6%、最小で0.5%、平均すると約2%程度含まれていることが判りました。
その後、パライバ・トルマリンはパライバ州以外でも発見されました。パライバ州の隣の州でも発見され、さらにアフリカのナイジェリアやモザンビークからも見つかりました。現在、ブラジルのパライバ州以外で産出する同様な色のトルマリンに対してもパライバ・トルマリンと呼称しています。ただし、銅とマンガンを含むこと、と規定されています。

変種
本体(ある石を形造っている化学組成あるいは構成している元素の割合)が同じで、いろいろな色で産出することを言います。トルマリンはいろいろな色で産出することが知られています。
鮮青色のパライバ・トルマリンも変種の一種です。この他にトルマリンは赤色、緑色、紫色、藍色、黒色などがあります。無色でも産出します。
宝石市場では赤色のトルマリンがよく知られています。市場ではルベライトという名称で流通しています。この石は少し黒色味を帯びた赤色です。
緑色のトルマリンはベルデライト、紫色はシベライト、藍色はインディゴライト、黒色はショール、無色はアクロアイトと呼ばれています。
変種はトルマリン以外でもあります。例えば、赤色のルビーと青色のブルー・サファイアも変種同士です。変種は英語表記ではバラエティといいます。
トルマリンは多くの変種を持っています。ですから、トルマリンのみで構成された色の変化に富むネックレスも売り出されています。多彩な色を持つトルマリンだからできる特長といえます。
焦電気(しょうでんき)
トルマリンを100℃(度)近くまで加熱すると、一方の端に正(プラス)電気、他の端に負(マイナス)電気が発生して帯電する現象が起こります。
その結果、トルマリンは周りの小さなホコリやゴミを引き付けます。このようなトルマリンの特性から、和名(日本語表記)は電気石と呼ばれています。そして、このような現象を焦電気といいます。
トルマリンが焦電気を持っていることは古くから知られており、オランダの宝石商人達はトルマリンのことを「灰を吸い付ける石」と呼んでいました。
二色性
トルマリンをある方向から見て、次にその方向を変えて見ると、色が変わって見えます。この現象は二色性と呼ばれています。
トルマリンは多彩な色を持つことで知られています。その中で緑色や褐色のトルマリンは特に二色性が強いです。ある方向では緑色や褐色に見え、方向を変えると真っ黒になります。方向によって驚くほど色が変わります。これほど劇的に色が変わる石は他にありませんから、トルマリンであると判定できます。
赤色のトルマリンであるルベライトも二色性を示します。しかし、緑色や褐色ほど強くありません。ルベライトのルース(裸石)の方向を変えて、10倍のルーペで観察すると、濃い赤色と淡いピンク色に見えます。確かに二色性を示します。
二色性の観察はガラスとの識別に役立ちます。ガラスには二色性はありません。例えば、赤色のガラスとルベライトを識別する場合、前者では二色性がありませんから、いろいろな方向から観察しても色は変わりません。後者では二色性がありますので、方向を変えると、色が変化します。
ダブリング
10倍のルーペを使って、ルースのテーブル面(中央の広い平らな面)から裏側のファセット(カット、研磨された平らな面)とファセットが接するライン(線)を観察すると、そのラインが二重に見える現象をいいます。
この現象を利用すると、ガラスとの識別に役立ちます。たとえば、ピンク・トルマリンとピンク色のガラスを識別する場合、ダブリングの有無で識別が可能です。ピンク・トルマリンではダブリングが見られます。しかし、ピンク・ガラスではダブリングが見られません。
ダブリング現象は多くの宝石で見られます。しかし、10倍のルーペでダブリングを観察できる石は限られます。トルマリンやペリドット、スフェーン、クンツァイトなどです。
このダブリング現象は石の複屈折に起因しています。複屈折とは光が二つに分かれることです。宝石に光が当たると、その光は宝石の中を透過します。そして光が透過するとき、一般にその光は二つに分かれて進みます。分かれる程度は宝石の種類によって違います。分かれる程度が大きいと、ダブリングという現象を10倍のルーペで観察することができます。
バイカラー・トルマリン
バイは二つという意味です。ですから、二つの色を同時に持っているトルマリンということになります。
トルマリンは多彩な色で産出することが知られています。その多彩な色の中のふたつの色が同時にひとつの石に現れた場合をバイカラー・トルマリンといいます。
例えば、長方形をしたルースの真中あたりで左右の色が、左では赤色、右では緑色と異なっているトルマリンがときどき市場で見られます。
さらにトルマリンの原石の断面を見ると、中心部が赤色で周囲が緑色をしたものもあります。この場合はウォーター・メロン(西瓜)と呼ばれています。